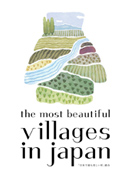- HOME
- わたしたちにとっての美しい村とは
- 群馬県昭和村
わたしたちにとっての美しい村とは?
- 群馬県昭和村 -
あなたにとって、美しい村とは?
「私にとっての美しい村」
朝、家の前の梅の木の小枝に止まる雀のさえずりで目が覚める。雨戸をあけ家の前方の地区境の小山の頂きがやがて昇り来るお日様の光で山のシルエットを映し出し、穏やかな今日一日の予感を占ってくれる。そんな朝で一日が始まる。
都会に近い地方では山里がなくなりつつあるが、我が村昭和村ではふるさとがまだ満ちあふれている。
私の生まれ育った村周辺には失われ行くかつての日本のふるさとの原風景が沢山ある。群馬県の北部に位置し、上毛三山として位置づけられている山の一つ「赤城山」の北麓にあるなだらかな高原の扇状地形の村だ。村境を流れる利根川と片品川の清流は小学生の頃の夏休みのほとんどを水泳ぎや魚釣りで費やした。裏山の雑木林に入りクワガタやカブトムシも沢山とった。川から田圃に水をひくために作った用水路のトンネルに秋の水のない時期を見はからって友達と冒険をしたり、村そのものが大自然のテーマパークだ。そしてそれらの一つ一つが今の私の想像力の糧となっている。
私の生まれ育った村の幼い頃の一年を思い出すとき、消えゆく「ふるさとの姿」がよみがえってくる。
一年の始まりは近くの1000m級の山へ登り初日の出「ご来光」を見ることから始まり、小正月は1月15日の未明に行われる「どんどん焼き」だ。眠い目をこすりながら河原に作られたお正月の門松などを処分するために作られた櫓のお焚き上げ行事に出掛けた。櫓が燃える火にあたるとその年一年間風邪をひかないと言われ子供も年寄りも一家総出で出かけ、会場では甘酒やお菓子がもらえた。2月の節分では一家の誰かが鬼になり豆をぶつけて邪鬼を追い払いその年の厄払いをした。そして家の中に散乱した投げた豆を拾い自分の年の数だけ食べるとその年一年病気にならないと言われ一家全員食べた。また、投げた豆を保存して置き夏の雷雨のとき、その豆を食べると落雷しないと言われ保存して置き雷雨の時食べた。冬の外の遊びは、女は羽根つき、男は凧あげやそり遊びで、凧あげでは誰が一番高く遠くまで上げることが出来るかを競った。そり遊びは自分で作ったソリを自慢し合った。スキーも太い竹をもらって4つ割にして2枚を針金でつなぎ合わせたスキーを自分で作り遊んだ。作る過程で手を切ったり金づちで指を叩いてどす黒くはれ上がって痛い目にあったが、その中から刃物の使い方を覚えることもできた。今の様にホームセンターなどなかったから遊びの道具は自分で作るより仕方なかった。作り方も誰も教えてくれない、先輩の物を見て自分で工夫して作った。また、雪中遊びなので寒かったろうが、今思い出してもその寒さの記憶が無い。楽しい思いの方が優先していたのだろう。
冬の川へ行き水の中の石の裏のカジカのたまご取りをした。そのたまごを塩漬けにしておき、夏の魚釣りの餌にした。その他メンコ遊びや、コマ回しをして遊んでいた。冬が過ぎ、桜の花が咲く頃になると各地区で春のお祭りが行われる。近くの氏神様では赤飯や菓子のお御供、神社では歌舞伎が行われ出店も出て小遣いをもらって見物に出かけた。歌舞伎の内容は良く理解できなかったがその雰囲気が楽しかった。
初夏、竹藪に若竹が伸びタケノコ時代に纏っていた皮が剥がれ出すと、その皮を拾い4束に集めて置くと町から業者がやって来て買っていってくれる。子供にしてはうれしい小遣い稼ぎとなった。夏休みには畑仕事の手伝いのほかはほとんど毎日川で水泳ぎと魚釣りで過ごしていた。50m位の川幅を泳ぎ切れば一人前と言われ小学校中学年の頃幾度も溺れそうになりながら挑戦した思い出がある。また山の遊びのカブトムシ取りやセミ取りも楽しかった。5寸釘を利用して遊んだ釘通しもお金の掛からないおもしろい遊びだった。先祖を敬い迎えるお盆も楽しい思い出がある。8月13日にお墓からお盆様を迎えるとその日の夕方はどこの家も「門火」を灯し先祖の来訪をもてなした。その日は子供達も花火びで戦争ごっこなどしたり、ガス鉄砲を鳴らして楽しんだ。夏休みも終わりに近くなったころ地区内の権現様では子供相撲が開催された。強くも弱くも全員がその成長ぶりを親兄弟に披露する行事で勝っても負けても文房具などの賞品がもらえた。子供のころの思い出は遊びだけではなかった。春夏秋冬の中で農作業の手伝いも春にはジャガイモや落花生、大豆の種まき、さつまいも植え。夏にはその草むしり、秋にはそれらの収穫作業や麦播きなど、子供の手作業ではかどりはしなかったが親には褒められた。働いた後の昼食の旨かった事が今でも忘れられない。今の様に気の利いた弁当ではない。ドカベンに麦飯ごはんが満タンに詰まっていて、おかずは梅干しと沢庵漬け、あとは生みそがあり、畑の生きゅうりや長ネギなどその生みそを付けて食べる。しまいにはご飯に水をかけ生みそを混ぜて食べる。今では考えられないことである。畑越しには奥利根地方の山々が眺望でき、子供ながらに「いつまでもこの村で暮らしていきたい」という思いも生まれてきた。秋になれば、さつまいもや大豆の採り入れを手伝いながら近くの山林でアケビ取りや栗拾いを楽しんだ。そして奥利根の山々は紅葉の錦に彩られる頃、どこに潜んでいたのだろうか2~3cmの小さな白い雪おやじ(雪虫)が飛び交い冬の訪れを告げ、やがて上越の国境の谷川岳に雪雲がかかり木枯らしと共に一気に冬の季節となり、一年が終わる。今は一年の終わりや一年の始まりはテレビやラジオ等で感じ取ることができるが、昔はどこの家でも餅つきが行われ、男達が臼の中のモチ米を突く力強い音で無事に過ぎていく旧年への「感謝」と訪れる新年への「期待」を子供ながらに感じることができた大事な行事の一つであり、後世の子供たちの為にも残しておきたい行事の一つだ。
美しい村を考えるとき「視覚的に感じる美しい村」と「感情的に感じる美しい村」があると思う。
視覚的に美しい村とは今自分の目の前に映し出される景色やまつりや環境などがある。私の村で言えば火山と川の浸食と隆起を繰り返して形づくられた日本でも有数の河岸段丘。なだらかな高原の畑地越しに眺望できる雄大な奥利根の山々。そしてそれらが四季折々に繰り広げる絵画の様な自然の営みの中で生きる悦びを感じる。
また、広大に広がるあちらこちらの畑や田圃では人々の生命の源である食料を生産する若い農業者達がエンジンの音高らかに大型トラクターを耕耘している光景を見るとき「この村では後継者不足という言葉は無縁なんだなア」と誇らしさを感じる。また、大自然の景色は勿論のこと、朝夕の通学路にランドセルを揺らしながら子供達が行き交う光景はこの村の希望を感じ私の大好きな風景でもある。
心理的に感じる美しいむらとは、子供の頃「遊び」や「まつり」や「伝統行事」などを体験したかしなかったかで違ってくるであろう。それらの数が多い程、心豊かで魅力ある人間になれる。遊びの中では、物作りの楽しさや先輩後輩の上下関係の大切さを養い、物作りの中では痛みや想像力を養う事が出来た。
まつりや伝統行事では自分が住む昔を知り、人々の協調心「つながり」を大切にすることが大事である事に気づいて行く。
時代が変われば、環境も変わり人々の営みも変わっていく。しかし、伝統ある「まつり」や「村の各地区総出で行われるのイベント」等を通して交流を深めて行くことで「いつでも一つになれる心」「助け合いの精神」は無くなることはないだろう。
村の魅力は自然が豊かであること。農業に誇りを持つ青年達が多くいること。伝統行事(大祭や奇祭含む) や村民総出のイベントなどが四季を通じ行われていること。子供達を大事にしていること、特に私の村では子供主体のまつり、奇祭と言われる「かつぎまんどう」がある。資金集めから、人形や人形を乗せる台座の制作、祭りの奉賀金(祝い金)分配などすべて子供たちの祭りのしきたりの中で行わせ、大人たちは一切口出しをしない。約2か月余りでまんどうを仕上げ、その地区の秋祭りの中で披露し各地区のまんどう同士をぶつけ合う「子供たちの成長を喜び合う」祭りで、全国でも珍しいまつりとして我が村が誇れる物の一つであり、何時までも続けてほしいと願っている。
東京の様な大都会だって「故郷」はある、そこに生まれそこで育ち子供のころに体験した遊びや伝統行事を体験したりそのしきたりを受け入れながら生きた思い出そのものが「故郷」となり、心の中に残っていくのだろうと思う。そしていつまでもその思い出深い風景がそのまま残っていれば何にも勝る故郷「美しい村」となるのではないだろうか。
群馬県昭和村 道の駅あぐりーむ昭和 倉澤新平